Go “HR” Transformation!
Go “HR”
Transformation!
テクノロジーで “働く” を変えていく。
テクノロジーで
“働く” を変えていく。
NEWS ニュース
SERVICE HR Forceにできること

データプラットフォーム事業
弊社が有する国内求人運用データから、お客様の課題解決に貢献します。

Indeed広告運用事業
indeedスポンサー求人の配信戦略から広告運用を実施。
※当社はIndeedゴールドパートナーの認定を受けております。

Recruiting Cloud リクルーティングクラウド
企業の求人情報を150以上の連携媒体から最もパフォーマンスの良い面に掲載する、求人プラットフォームサービス。導入社数7,000社以上(2023年7月現在)
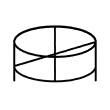
Azapt アザプト
データ分析環境の導入から採用データの集約・管理・分析・広告運用までをワンストップでサポートするサービス。
※2023年8月リリース
今、最も選ばれる採用ツール

CASES 成功事例
累計7,000社以上の企業様に
導入いただいています
CONTACT お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
HR Forceはテクノロジーで、
世界のHRシーンをリードしています。
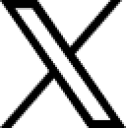
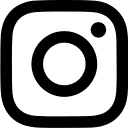
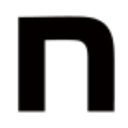


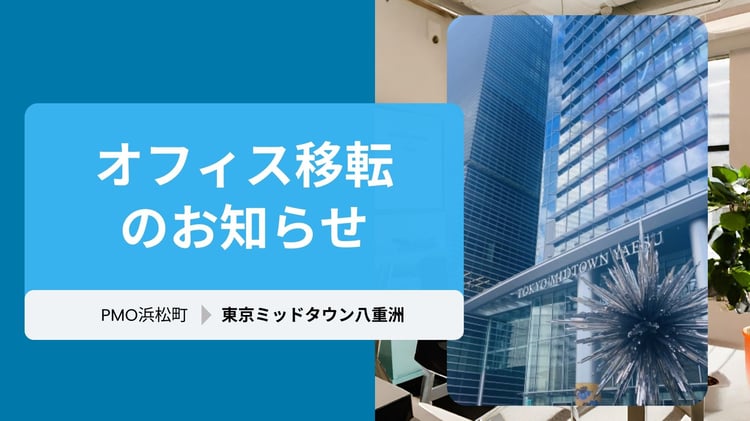
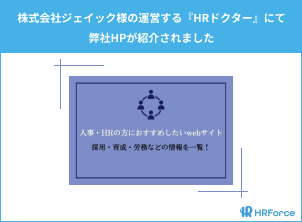




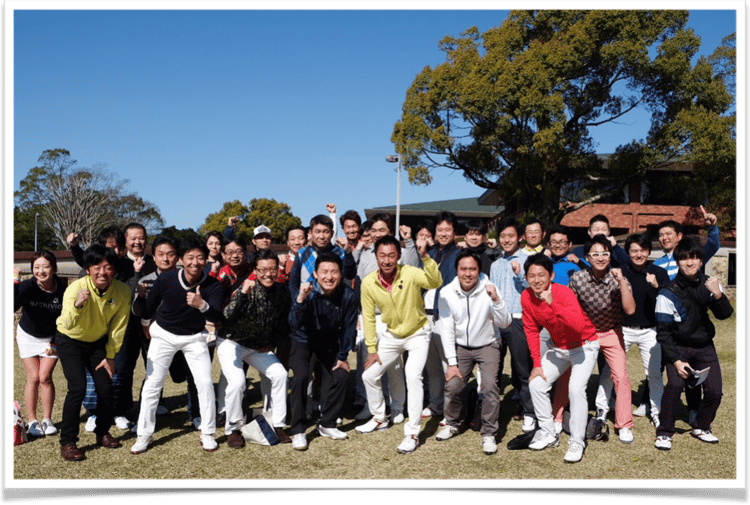








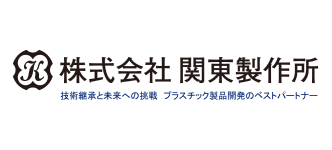





%20(1).png)
%20(1).png)